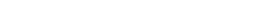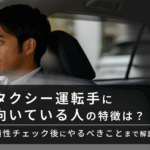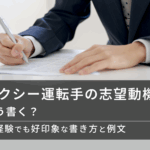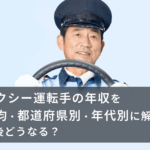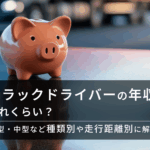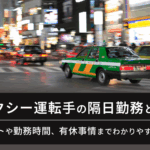サイトからのお知らせ
2025/08/26
タクシー運転手の隔日勤務とは?シフトや勤務時間、有休事情までわかりやすく解説
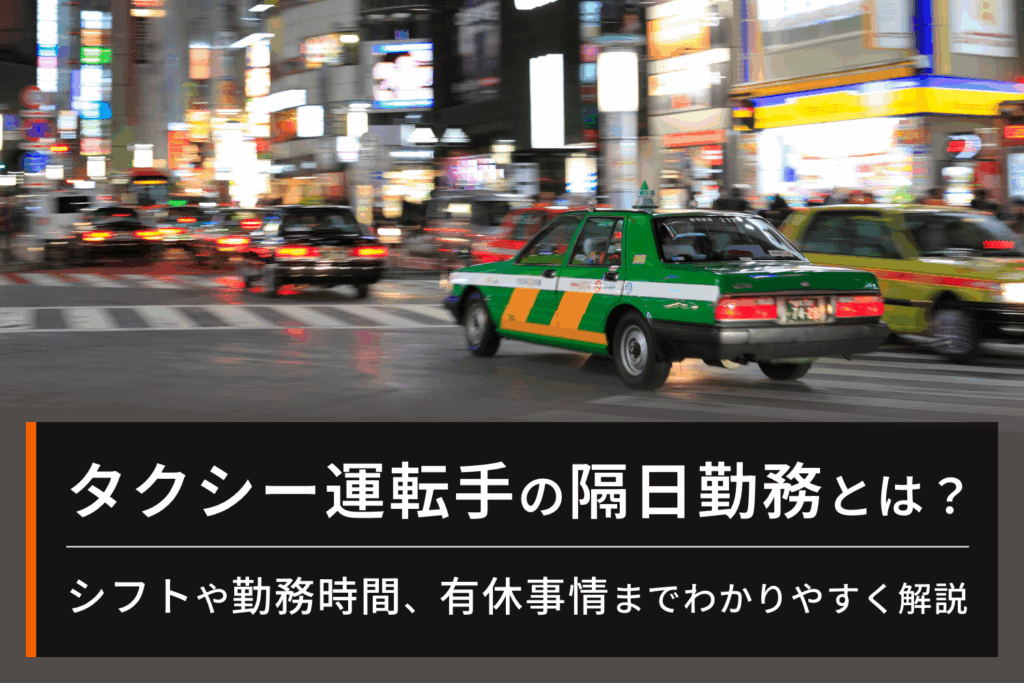
タクシー運転手の主な働き方のひとつに「隔日勤務」があります。名前は聞いたことがあっても、実際どのような働き方なのか気になる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、隔日勤務の仕組みやシフト例、有給休暇の取りやすさ、きついと言われる理由までわかりやすく解説します。隔日勤務が向いている人の特徴も紹介しますので、タクシー運転手を目指す方はぜひ参考にしてください。
タクシー運転手の隔日勤務とは?

隔日勤務とは、1日働いた翌日を休みにするタクシー運転手特有の勤務形態です。月の勤務回数は11〜13回ほどで、1回の勤務時間は通常16〜21時間程度と長めになります。
勤務翌日の休みは「明け番」と呼ばれ、法律では22時間以上の休息を確保することが義務付けられており、24時間の休息確保が努力目標とされています。この「明け番」は隔日勤務特有の制度であり、日勤や夜勤には適用されません。
さらに隔日勤務には、明け番のほかに通常の休日(公休)も設けられているため、月の半分以上が休みになるのが特徴です。勤務時間が長い一方で、翌日がしっかり休めるため、プライベートの時間を確保しやすく、家族との時間や趣味の時間を充実させたい人にも向いた勤務形態といえるでしょう。
一般の昼夜勤務とどう違う?
隔日勤務は「2日分の仕事を1日にまとめて行い、翌日休む」勤務形態です。翌日は必ず休みになるため、自由時間を確保しやすい反面、1日の拘束時間と負担が大きいのが特徴です。
一方、昼夜勤務は1日8時間程度の労働を週5日(週休2日)で繰り返す働き方です。日勤は午前から夕方まで、夜勤は夕方から深夜までが基本で、会社員に近い生活リズムを維持できる点がメリットでしょう。
隔日勤務は長時間勤務の負担はあるものの、まとまった休みを取りやすいため、自己管理ができる人や自分の時間を重視する人に向いています。
一方で昼夜勤務は生活リズムを整えやすく、体力的な負担が少ないため、規則正しい生活を送りたい人や体力に自信がない人に適しているといえるでしょう。
隔日勤務のシフトやスケジュール例

隔日勤務は一般的な会社員の勤務形態とは異なるため、具体的なスケジュールが気になる方も多いでしょう。
隔日勤務の一般的な勤務時間例は以下の通りです。
・7:00出勤~翌3:00退勤
・14:00出勤~翌8:00退勤
タクシー会社によって出勤・退勤時間は異なりますが、翌日まで勤務が続き、その翌日は明け番(休み)となるのが基本です。例えば、月曜の朝から火曜未明まで勤務した場合、火曜は明け番として完全オフとなり、次の勤務は水曜となります。
スケジュールの流れは「勤務(出番)→明け番(休み)→勤務→明け番→公休」というパターンが一般的で、出番と明け番を2回繰り返した後、公休と組み合わせて2連休を取るサイクルが多く見られます。
例:月曜(勤務)→火曜(明け番)→水曜(勤務)→木曜(明け番)→金曜(公休)→土曜(勤務)
なお、これはあくまで一例であり、タクシー会社によっては月に3〜4連休を取得できる場合もあります。休日を多く取りたい方にとって、隔日勤務は選択肢のひとつとなるでしょう。
実際の1日の流れ:出勤〜休憩〜帰庫〜日報提出
隔日勤務の1日の流れを見ていきましょう。
隔日勤務では、早朝または午後に出社し、点呼やアルコール検査、車両点検を行ったあとに営業を開始します。営業中は休憩を挟みながら、昼・午後〜夕方・夜間〜深夜・早朝と時間帯ごとの乗客に対応し、翌日に帰庫して業務終了となるのが基本の流れです。
隔日勤務の基本的な流れは次の通りです。
- 出勤・点呼・車両点検
早朝や午後に出社し、点呼・アルコール検査・車両点検を行い準備を整えます。
- 営業開始
朝〜夕方は通勤や買い物客、夜間〜早朝は繁華街や夜勤帰りの乗客など時間帯に応じた送迎を行います。
- 適宜休憩
食事や仮眠を取りながら無理なく営業を続けます。
- 帰庫・精算
深夜〜翌朝に営業を終え、車両清掃・点検・売上精算・日報提出を済ませて退社します。
長時間勤務にはなりますが、翌日は必ず休みになるため、自由な時間を確保しやすいのが隔日勤務の特徴です。
具体的な早朝出勤・午後出勤それぞれの隔日勤務の1日の流れをまとめましたので、詳しくは表をご覧ください。
01-1024x652.png)
02-1024x475.png)
01-1024x652.png)
02-1024x475.png)
勤務時間と法定労働時間の関係

タクシー運転手の隔日勤務は、厚生労働省の「改善基準告示」に基づき以下のルールが設けられています。
- 1回の勤務の拘束時間は 最大22時間以内(2回の勤務で平均21時間以内)
- 月の拘束時間は 262時間以内(労使協定で最大270時間まで延長可)
- 勤務後は 原則24時間以上の休息(最低でも22時間以上)
本来の労働時間は「1日8時間・週40時間」が基本ですが、タクシー運転手の隔日勤務は変形労働時間制を活用し、月・年単位で平均8時間以内となるよう調整しています。そのため、1回の勤務時間は長いですが、翌日が休みになるサイクルでバランスを取っているのです。
有給休暇は取得できる?休みの取りやすさは?

タクシー運転手も労働基準法の適用を受けるため、入社から6ヶ月勤務し出勤率が8割以上であれば有給休暇を取得可能です。初年度は年間10日付与され、勤続年数に応じて最大20日まで増えます。
また、タクシー運転手は個人業務が中心のため、急な休みでも他の社員に迷惑がかかりにくく、有給が取りやすい環境にあります。
注意点は、有給休暇の賃金計算方法です。労働基準法により「平均賃金」などで計算されますが、具体的な方法は会社の規定で決まります。たとえば「前月の日額給与の80%」などが設定されている場合もあります。入社前に就業規則や労使協定を確認し、有給取得時の支給方法を把握しておくと安心です。
隔日勤務はきつい?向いている人・向いていない人

隔日勤務は休みが多いメリットがある反面、長時間勤務や生活リズムの乱れで「きつい」と感じる人もいます。ここでは、隔日勤務の向き不向きを整理します。
【きついと感じる理由】
隔日勤務がきついとされる理由は次の3点です。
・日中から翌朝まで働くため体調管理が難しくなりやすい
・拘束時間が15〜21時間と長く、体力・集中力が削られる
・勤務日と休日のサイクルが一般的な生活とずれ、家族や友人と予定を合わせにくい
特に、長時間の運転や夜間勤務が続くことで眠気や疲労を感じやすくなる点が大きな負担となるでしょう。
【向いている人】
隔日勤務が向いている人の特徴は以下の通りです。
・自己管理ができ、体調・生活リズムを調整できる人
・休みの多さを重視する人
・趣味や副業など仕事以外の時間を確保したい人
隔日勤務は勤務日こそ長いものの、月の半分以上が休みになるため、自分の時間を重視したい人にとって大きなメリットとなります。自己管理を徹底できる人であれば、隔日勤務はプライベートとの両立がしやすく、働きやすい勤務形態といえるでしょう。
どんな人がタクシー運転手に向いているかは、こちらの記事で詳しく解説しています。
『タクシー運転手に向いている人の特徴は?適性の確認後にやるべきことまで解説』
距離が長いときの対策と制度

隔日勤務中は、疲労防止のため1乗務あたり3時間の休憩取得が義務付けられています。長距離の乗車が続くと判断力が低下し事故リスクが高まるため、タクシー会社は適切な休憩を促し、無理な乗務をさせないよう管理しています。
また最近では、AIによる自動配車システムや高性能ナビの導入で無駄な走行が減り、運転手の負担が軽減されています。今後も最新技術の普及や運行管理の徹底により、長距離乗車時の疲労軽減が期待されるでしょう。
隔日勤務は「自由時間の多い働き方」
隔日勤務は拘束時間が長く大変に見えますが、実際は自由度が高く、休みが多いのが特徴です。休憩や体調管理は必要ですが、生活リズムを整えられれば長く続けやすい働き方といえるでしょう。
タクシー運転手を目指す際は、隔日勤務の特徴を理解した上で、自分のライフスタイルに合うかどうかを検討してみてください。
タクシー運転手の求人・転職先をお探しの方は、ドライバー・運転手専門の転職サイト『ドライバーの転職ナビ』がおすすめです。