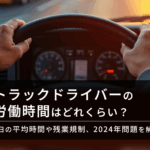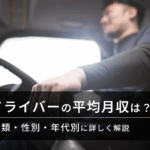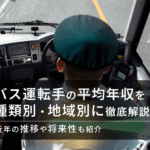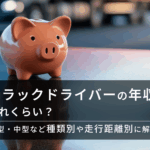サイトからのお知らせ
2025/04/30
2級自動車整備士の試験内容と受験資格、難易度を解説!

2級自動車整備士は、車の幅広い整備に関する仕事ができる国家資格です。資格を取得すると、待遇面も3級より優遇されます。初級の「3級」から最上級の「1級」まである自動車整備士資格の中で、一番取得者が多いのがこの「2級」。3級よりも求められるスキルが高くなりますが、その分整備士としてステップアップできる重要な資格といえます。
この記事では、2級自動車整備士の特徴や仕事内容、試験の内容、難易度についてわかりやすく解説します。
・自動車整備士のなり方や資格について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
『自動車整備士になる方法は?整備士に必要な資格と勉強法を解説』
『自動車整備士の資格の種類は?取得方法や試験の難易度も解説!』
2級自動車整備士の仕事内容とは

2級を持った整備士は、車のさまざまなトラブルやメンテナンスに対応できます。整備士の約8割がこの資格を持っていると言われ、それだけ需要の高いスキルでもあります。
2級自動車整備士には、以下のような種類があります。
- 2級ガソリン自動車整備士
- 2級ジーゼル自動車整備士
- 2級自動車シャシ整備士
- 2級二輪自動車整備士
2級自動車整備士が行える整備業務は、主に次のようなものにます。
- エンジンやブレーキシステムなどの点検作業
- オイル交換や消耗品替えなどの定期整備
- 電装系のトラブル解決
- エンジンや足回りの部品を分解して整備
特にエンジンや車体の分解整備ができる点が、3級整備士との大きな違いです。このスキルが上がることで、より専門性が高い仕事を行えるようになります。
・3級自動車整備士について詳しく知りたい方はこちらの記事を詳しく解説しています。
『3級自動車整備士の試験内容と受験資格、難易度を解説!』
2級自動車整備士の資格には、2級自動車シャン整備士、2級自動車ガソリン整備士、2級自動車ジーゼル整備士、2級二輪自動車整備士の4つがあり、それぞれ対応可能な整備が異なります。
2級自動車シャシ整備士は、普通自動車や四輪・三輪の小型自動車、軽自動車のシャシ部分の整備を行うことができます。ガソリンエンジンを搭載した普通自動車などの整備を行うのが2級自動車ガソリン整備士、ジーゼルエンジンを搭載した普通自動車などの整備を行うのが2級自動車ジーゼル整備士となります。また、オートバイなどの二輪車のエンジンやブレーキ、フレームなどの分解整備を含む整備を行うのは2級二輪自動車整備士となります。
この4つの資格のなかで、最も受験者数が多いのは2級自動車ガソリン整備士で、次に2級自動車ジーゼル整備士が多くなっています。
4つの資格の特徴をまとめると次の表のようになります。

これによって、関わりたい車種や分野に特化したスキルを習得しやすいのが特徴です。
ただし、自動車検査員としての業務や、より高度で専門性の高い整備(1級の分解修理や検査員としての業務など)を担当するためには、もっと上の資格が必要になる点も覚えておきましょう。
2級は整備士への道の中でも大きなステップになりますが、後々「1級」を目指すための基礎固めにも大切な資格です。
・1級自動車整備士についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
『1級自動車整備士の試験内容と受験資格、難易度を解説!』
2級自動車整備士の受験資格

2級自動車整備士の受験資格は、学歴や実務経験に応じた条件があります。
- 専門学校や養成施設の「2級整備士養成課程」を修了した場合 → 卒業と同時に受験資格を得られる
- 自動車整備系の専門学校や機械工学科を卒業した場合 → 3級整備士資格取得後に整備工場やディーラーでの2年間の実務経験が必要
- 大学や高等専門学校の機械工学科を卒業した場合 → 3級取得後に1年6ヵ月以上の実務経験が必要
- 機械工学科以外の学校を卒業した場 → 3級取得後に3年以上の実務経験が必要
必要な実務経験の長さは、卒業した学科や学校によって異なるため、自分の状況に応じた条件を確認することが大切です。また、実務経験の場は国土交通省が指定した工場や認定工場でのみ有効です。働く場所選びもよく調べて決めましょう。
2級自動車整備士の試験内容と難易度
自動車整備士の資格には、1級・2級・3級の3つがあります。この中で、2級は3級より難しいものの1級よりは簡単な中級レベルです。試験は毎年2回行われ、それぞれ学科試験が2回、実技試験が1回の合計3つの試験を受ける必要があります。
具体的な試験内容についてまとめました。
試験内容について

学科試験は、2級ガソリン・ジーゼル・二輪と2級自動車シャシに分かれており、それぞれ該当する筆記試験を受けます。2級ガソリン・ジーゼル・二輪 は40問、2級自動車シャシは30問からなる選択式問題が出題され、それぞれの合格ラインは40点満点中28点以上、30点満点中21点以上が目安です。
学科試験は次の4つの分野に分かれます。
- 2級自動車シャシ科目
- 2級ガソリン科目
- 2級ジーゼル科目
- 2級二輪科目
合格率について
日本自動車整備振興会連合会が公表している令和4年~6年のデータでは、学科試験の平均合格率は以下の通りです。
- 2級自動車シャン整備士の合格率:約73~86%
- 2級自動車ガソリン整備士の合格率:約60%
- 2級自動車ジーゼル整備士の合格率:約50~60%
- 2級二輪自動車整備士の合格率:約73~80%
筆記に比べて実技は難易度が高く、2級自動車ガソリン整備士の合格率は約41%、2級自動車ジーゼル整備士の合格率は約33%と低くなっています。ただし、養成施設で所定の課程を修了した場合などにおいて実技試験そのものが免除されることも多く、年によって大きく変動するため、合格率はあくまでも目安程度に留めておきましょう。
2級の筆記・実技を合わせた最終的な合格率は約40%~90%で幅があります。
- 3月の試験は合格率が高め。専門学校生など多くが受験するからです。
- 8月の試験は合格率が低い。独学で挑む方が多く、準備が間に合わないケースが目立ちます。
とはいえ、2級はしっかりと試験対策をすれば合格しやすい資格ですので、合格率は参考程度にしておきましょう。
試験対策の方法について
自分でできる受験対策としては、自動車整備振興会が発行している教科書を購入したり、自動車整備振興会のサイトに掲載されている過去問を解く方法があります。また、自動車整備に役立つスマートフォンのアプリもたくさんあるので、それらを活用して学習を進めるのもよいでしょう。
実技試験については、各都道府県の自動車整備振興会が開催している講習などがとても役立ちます。2級自動車整備士向けの講習を受講するには、3級自動車整備士の資格を保有していることや、一定の実務経験を積んでいることが求められます。この講習に参加することで実技試験が免除されることもあり、残りの勉強時間を筆記試験対策に集中しやすくなります。
ぜひ、効率的に準備を進め、2級自動車整備士の資格取得を目指してください。
2級自動車整備士の資格を取得するメリット

2級自動車整備士の資格を取得することで、仕事にも収入にも、いろいろなプラスが得られます。
まず、2級を取得することで携われる仕事が一気に増えるのが大きなポイントです。3級自動車整備士は主にオイル交換などの基礎的な作業だけですが、2級を持っていると、エンジンやタイヤ周りの本格的な修理・整備、さらに板金塗装なども担えるようになります。また、整備主任など役職につくチャンスもあり、工場で欠かせない存在として重宝されるでしょう。
さらに、2級を取得していることで、その先の上位資格にも挑戦できます。たとえば、車検の合否を判断できる自動車検査員の資格や、実務経験を積んで「1級自動車整備士」を目指すことも可能です。1級を取るとさらに仕事の幅も広がり、ステップアップにつながります。
給料面でも2級を取得するメリットがあります。2級を持っている人の平均年収は約380~420万円。一方、3級は300~350万円あたりなので、2級を取れば給与が数十万円アップする可能性があります。なお、1級の平均年収は420万円ですが、2級との差はそれほど大きくなく、コスパのよい資格と言えるでしょう。
全体的に、2級は1級ほど難しいわけではない上に、業務範囲が広がり、お給料も増やせる資格です。それに加えて、そこまで取るのが難しくない点も魅力となっています。
・自動車整備士の収入についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
『自動車整備士の給料はいくら?整備士で高い給料を目指す方法』
1級との違いを理解しながら2級の魅力を最大限活かそう
2級自動車整備士の資格を取得すると、幅広い整備業務が担当できるようになり、キャリアや待遇の面でも優遇されるようになります。
多数のメリットがある一方、試験の難易度はそこまで高くないため、しっかり準備して受験に臨めば合格しやすい資格である点も魅力でしょう。年収の面で1級と大きな差がないなど、難易度と取得後のメリットのバランスがよいため、8割以上の自動車整備士が取得しています。
自動車整備士として働くなら、2級自動車整備士になることを1つの目標とするとよいでしょう。
・自動車整備士への転職をお考えの方は、自動車整備士専門キャリアアドバイザーのサポート付き自動車整備士の転職サイト『メカニック転職ナビ』がおすすめ!