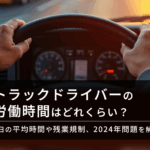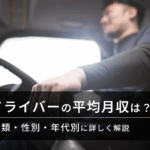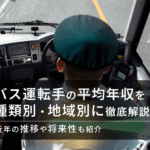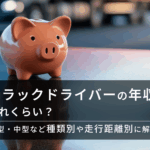サイトからのお知らせ
2025/04/30
3級自動車整備士の試験内容と受験資格、難易度を解説!

3級自動車整備士は、整備士として基本的なスキルを学び、実践するための最初のステップとなる資格です。特に、整備の仕事をしながら資格を取りたいという人が目指すことが多く、この資格を取ることで整備士への一歩を踏み出せます。将来的には、この3級資格をもとにさらに上位の資格を目指すこともできます。
この記事では、3級自動車整備士について、仕事内容や受験資格、試験の難易度について解説します。
・自動車整備士のなり方や資格について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
『自動車整備士になる方法は?整備士に必要な資格と勉強法を解説』
『自動車整備士の資格の種類は?取得方法や試験の難易度も解説!』
3級自動車整備士の仕事内容

3級自動車整備士は、車の整備に必要な基本的なスキルを持つことを証明する、国家資格の初歩的なレベルです。この資格を取得すると、車両点検や簡単な整備作業を任されるようになります。
3級自動車整備士には、以下の種類があります。
- 3級自動車シャシ整備士
- 3級自動車ガソリン整備士
- 3級自動車ジーゼル整備士
- 3級二輪自動車整備士
3級自動車整備士が行える整備業務は、主に次のようなものになります。
- エンジンオイルやギアオイル、タイヤの交換
- ブレーキやライトの機能確認
これらの整備業務は車のメンテナンスにおいて必須の作業であり、これらを行えるかどうかで整備士としての仕事の範囲が変わってきます。
無資格の場合だと、整備できる範囲がとても制限されてしまいます。例としてエンジンオイルの交換やタイヤ交換など簡単な仕事も、資格を持つ整備士の監督が必要になるなど、自由度が低くなります。
一方で、3級自動車整備士の資格があれば、一定範囲内で自分で整備作業を進められるのが大きな利点です。
3級自動車整備士の資格には、3級自動車シャン整備士、3級自動車ガソリン・エンジン整備士、3級自動車ジーゼル・エンジン整備士、3級二輪自動車整備士の4つがあり、それぞれ整備できる範囲が異なります。
3級自動車シャシ整備士は、主に普通自動車などのシャシ部分の基本的な整備を行うことができます。
ガソリンエンジンを搭載した普通自動車などの基本的な整備を行うのが3級自動車ガソリン・エンジン整備士、同じくジーゼルエンジンを搭載した普通自動車などの整備を行うのが3級自動車ジーゼル・エンジン整備士となります。
また、オートバイなどの二輪自動車の基本的な整備を行う場合は3級二輪自動車整備士となります。
この4つの資格のなかで、もっとも受験者数が多いのは3級自動車ガソリン・エンジン整備士で、次に3級自動車シャシ整備士が多くなっています。
4つの資格の特徴をまとめると次の表のようになります。

3級の資格でできる作業は基本的な整備が中心で、例えばエンジンを分解したり、タイヤ周りの複雑な修理を行うような高度なスキルが求められる作業には対応できません。
しかし、この資格は、将来さらにスキルを身につけ、2級や1級などの上位資格を目指すためのスタートラインと言える存在です。
・1級自動車整備士・2級自動車整備士についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
『1級自動車整備士の試験内容と受験資格、難易度を解説!』
『2級自動車整備士の試験内容と受験資格、難易度を解説!』
3級自動車整備士の受験資格

3級自動車整備士の受験資格は、学歴や実務経験に応じた条件があります。
- 自動車整備系の高校や専門学校を卒業した場合 → 試験はすべて免除され、卒業時に資格取得
- 自動車整備系の専門学校や機械工学科を卒業した場合 → 整備工場やディーラーで6ヵ月以上の実務経験が必要
- 機械工学科以外の学校を卒業した場合 → 1年以上の実務経験が必要
必要な実務経験の長さは、卒業した学科や学校によって異なるため、自分の状況に応じた条件を確認することが大切です。また、実務経験の場は国土交通省が指定した工場や認定工場でのみ有効です。働く場所選びもよく調べて決めましょう。
3級自動車整備士の試験内容と難易度
自動車整備士の資格には、1級・2級・3級の3つがあります。この中で、3級はもっとも難易度が易しくなっています。試験は年2回実施され、それぞれ学科が2回、実技が1回の計3回受ける必要があります。
具体的な試験内容について表にまとめました。
試験内容について

<学科試験>
学科試験では、自動車整備に関する基礎的な知識が50分間のマークシート形式で問われます。試験は全部で30問出題され、21点以上を取れば合格となります。
<実技試験>
学科試験に合格できた人が次に実技試験を受けられます。ここでは、簡単な部品の分解・組み立てや点検作業、調整作業を通じて整備の基本的技術を実践的に問われます。
ただし、所定の施設であらかじめ必要な研修を受けた人の場合、実技試験が免除されることもあるため、自分の状況を確認しておきましょう。
合格率について
日本自動車整備振興会連合会が公表している令和4年~6年のデータでは、学科試験の平均合格率は以下の通りです。
- 3級シャシ:約60~70%
- 3級ガソリン:約65~74%
- 3級自動車ジーゼル:約60~65%
- 3級2輪:約83~84%
半数以上の受験者が合格している学科に比べ、実技は難易度が高く、3級自動車シャン整備士は約48%~83%、3級自動車ガソリン・エンジン整備士は約57%となっています。
ただし、実技試験は、養成施設で所定の課程を修了した場合などは、実技試験そのものが免除されることも多く、年によって大きく変動するため、合格率はあくまでも目安程度に留めておきましょう。
学科・実技を合わせた最終的な合格率は約60%~80%で、受験対策さえしっかりしていれば、比較的合格しやすい資格といえます。
試験対策の方法について
自分でできる試験対策としては、自動車整備振興会が発行している教科書を購入したり、自動車整備振興会のサイトに掲載されている過去問を解く方法があります。また、自動車整備に役立つスマートフォンのアプリもたくさんあるので、それらを活用して学習を進めるのもよいでしょう。
すでに1年以上の実務経験がある場合は、自動車整備振興会が主催する整備士技術講習への参加もおすすめです。講習はレベル分けされており、3級に該当する講習もあるため、試験対策として活用できます。
3級自動車整備士の資格を取得するメリット

3級自動車整備士の資格を取得すると、整備の基本に携われるようになるほか、キャリアの面で2つのメリットがあります。資格がなくても整備士として働くことはできますが、その場合はできる仕事が限られてしまい、キャリアパスや収入アップの面で発展性があまりありません。
<メリット1>
3級を取ると、2級や1級といった上の資格にチャレンジできるようになります。資格なしでは受験すらできません。3級は、よりキャリアアップを目指す人にとっての“第一歩”となる重要な資格です。
<メリット2>
就職・転職の幅が広がる点です。3級は初歩的な資格とはいえ、無資格よりも整備工場やディーラーから信頼されやすく、雇用のチャンスが増えます。基本的な整備業務なら即戦力になるため、労働力としても評価されやすくなるでしょう。
給与面では、3級自動車整備士の平均年収は約300~350万円となっています。2級・1級の平均年収は約380~420万円なため、年収で数十万円の違いがあります。収入を上げたり、できる仕事を増やしたい場合は、2級や1級も視野に入れて勉強するのがおすすめです。
・自動車整備士の収入についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
『自動車整備士の給料はいくら?整備士で高い給料を目指す方法』
3級自動車整備士は自動車整備士になるための第1歩
3級自動車整備士は、自動車整備士の中でも最初の段階にあたる国家資格です。資格を取得すると、各種オイルやタイヤの交換をはじめ、ブレーキやライトの機能確認といった基本的な整備を行えるようになります。
3級だけだとできる作業はあまり多くありませんが、3級取得後に一定の実務経験を積むことで、上位資格である2級自動車整備士の受験資格が得られます。2級を取得すればできる仕事の幅が広がり、給料などの待遇ももっとよくなります。
整備士として働きたいなら、まずは3級から挑戦し、そのあと上位資格を目指して成長していくのがよい方法です。
・自動車整備士への転職をお考えの方は、自動車整備士専門キャリアアドバイザーのサポート付き自動車整備士の転職サイト『メカニック転職ナビ』がおすすめ!